定年後に受け取る「退職金」は、老後の生活を大きく左右する大切な資金です。
しかし、「一括」で受け取るべきか、それとも「分割」で年金のように受け取るべきか――迷う方も多いのではないでしょうか?
さらに、受け取り方次第で税金の額や手取り金額が大きく変わることもあるのです。
本記事では、退職金を最大限に活かすための「受け取り方の選択肢」と「運用の基本」、そして「注意すべきポイント」をわかりやすく解説します。
読後には、あなたに合った受け取り方法を考えるヒントが得られるはずです。
💡 この記事を読むと分かること👇
退職金は「一括・分割・運用」を組み合わせて最大化する
退職金は、老後生活を豊かにするための貴重な資金です。
この大切なお金をただ受け取るだけでなく、戦略的に活用することで、その価値を最大限に高められます。
では、具体的にどのように考えればよいのでしょうか?
退職金は「受け取り方」で手取り額が変わる
退職金の受け取り方には、大きく分けて「一時金」として一括で受け取る方法と、「年金」として分割で受け取る方法の2つがあります。
多くの場合、退職金は「退職所得」として優遇された税制が適用されるため、一括で受け取る方が税金は安くなる傾向にあります。
しかし、分割で受け取った方が、運用益を含めて最終的な受取総額が多くなるケースも存在するのです。
一括・分割・運用のメリットを組み合わせるのが最適
最も理想的なのは、「一括」と「分割」それぞれのメリットを理解し、さらに「運用」を組み合わせて資産を増やすことです。
たとえば、生活費として必要な分を「年金形式」で少しずつ受け取り、当面使う予定のない資金を「一時金」として受け取って、安全な方法で運用するといった組み合わせが考えられます。
大切なのは、どれか一つを選ぶのではなく、あなた自身のライフプランに合わせて最適なバランスを見つけることなのです。
損を防ぐには税金と生活設計を意識する
退職金を受け取る際に最も意識すべきなのは、税金と老後の生活設計です。
一括で受け取った場合、「退職所得控除」という大きな控除が適用されます。
勤続年数が長いほど控除額も大きくなるため、ほとんど税金がかからないケースも珍しくありません。
一方で、年金形式で受け取った場合、公的年金等と合算して「公的年金等控除」が適用されますが、年間の受取額が大きくなると所得税や住民税が高くなる可能性があります。
また、退職金を「生活費」として見なすか、「資産」として増やすかによっても考え方は変わります。
現在の貯蓄額や将来の支出を考慮し、どれくらいのお金が必要で、どれくらいを運用に回せるかを検討することが、退職金を最大限に活かす第一歩となるでしょう。
退職金の受け取り方と税金の仕組み

退職金を受け取る前に、まずはそれぞれの受け取り方の特徴と、税金の仕組みについて深く理解しておきましょう。
一括受け取り(一時金)のメリット・デメリット
一括受け取りは、退職金を一度に全額受け取る方法です。
メリット
- 税制上の優遇措置が大きい:「退職所得控除」が適用され、税負担が軽くなるケースが多いです。勤続年数が長ければ長いほど控除額が大きくなります。
- 資産運用に回せる:まとまった資金をすぐに運用に回せるため、積極的な資産形成が可能になります。
- 手続きがシンプル:手続きが一度で済むため、煩雑な手間がかかりません。
デメリット
- 浪費のリスク:まとまったお金が手元にあるため、計画性のない使い方をしてしまうリスクがあります。
- 資産運用失敗のリスク:運用に回した場合、元本割れや資産が目減りするリスクが伴います。
分割受け取り(年金形式)のメリット・デメリット
分割受け取りは、退職金を年金のように毎月または毎年、一定額を受け取る方法です。
メリット
- 計画的な生活:定期的に収入があるため、老後の生活設計が立てやすくなります。
- 受け取り総額が増える可能性:分割して受け取るまでの間、運用されながら支払われるため、運用状況によっては一括受け取りよりも総額が多くなることがあります。
- 浪費を防ぐ:一度に大金が手元に来ないため、無計画な支出を防げます。
デメリット
- 税金が高くなる可能性:毎年受け取る年金は公的年金等と合算して課税されるため、受け取り額によっては所得税・住民税の負担が大きくなる可能性があります。
- 受け取り総額が減る可能性:運用状況によっては、受け取り総額が一括受け取りを下回ることもあります。
- 手続きが継続する:定期的な確認や手続きが必要になる場合があります。
税金の基礎知識|退職所得控除と課税方法の違い
退職金にかかる税金を理解する上で、最も重要なのが「退職所得控除」です。
これは、退職金の収入から差し引かれる控除のことで、この控除額を引いた残りの金額の半分にだけ税金がかかるという、非常に大きな優遇措置なのです。
退職所得控除額の計算方法
- 勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数−20年)
【例】勤続38年、退職金1,100万円の場合
800万円+70万円×(38年−20年)=800万円+70万円×18年=2,060万円 退職所得控除額は2,060万円となります。
この場合、退職金の金額(1,100万円)が控除額(2,060万円)を下回るため、課税所得は0円となり、税金はかかりません。
このように、多くのサラリーマンの場合、退職金にはほとんど税金がかからないケースが多いのです。
一方、年金形式で受け取る場合は、「公的年金等控除」が適用されます。
この控除額は、年齢や公的年金等の収入額によって決まります。
年間の受け取り額が一定額を超えると、税金負担が増える可能性があるため注意が必要です。
実例から学ぶ退職金活用のリアル
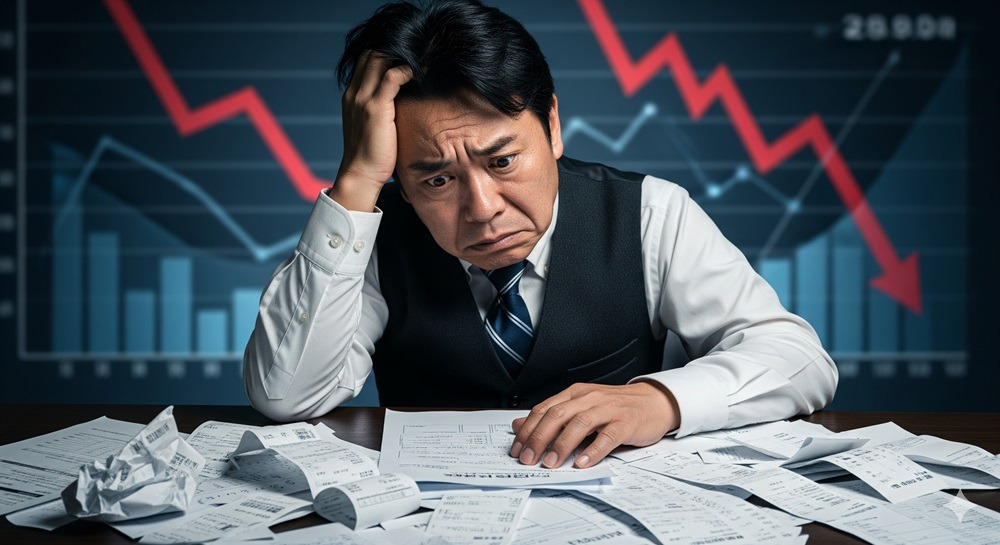
退職金に関するよくある失敗は、多くの場合、知識不足や計画性のなさから生じます。
あなたも同じような状況に陥らないよう、具体的な失敗例を3つご紹介しましょう。
「一括で受け取って浪費」してしまった例
Aさん(60代男性)は、長年勤めた会社を定年退職し、1,000万円の退職金を一括で受け取りました。
退職金という大金が手元に入った安心感から、以前から欲しかった趣味の道具や高級旅行を立て続けに購入。
しかし、老後の生活費を見積もっていなかったため、わずか数年で貯金が底をつき、結局、再就職を余儀なくされました。
【教訓】
手元に大金が入ると、つい気が大きくなってしまいがちです。
退職金は「ご褒美」ではなく、「老後の生活を支える資産」であることを忘れてはいけません。
事前にライフプランを立て、必要な生活費を明確にしておくことが大切なのです。
「分割受け取り」で予想以上に税金が高かった例
Bさん(60代女性)は、退職金を年金形式で受け取ることを選択しました。
退職金年金に加えて公的年金も受け取っていたため、年間の収入が予想以上に増えてしまいました。
その結果、所得税や住民税の負担が重くなり、手取り額が思ったより少なくなってしまったのです。
【教訓】
年金形式の受け取りでは、公的年金と合算した収入額が、税金の計算に影響します。
安易に「毎月少しずつもらえるから安心」と考えるのではなく、年金収入のシミュレーションを行い、税負担を事前に把握しておくことが重要でしょう。
「運用リスクを軽視」して失敗した例
Cさん(60代男性)は、退職金の一部を資産運用に回すことにしました。
友人から勧められた、リスクの高い投資商品に全額を投じてしまいましたが、景気後退の煽りを受けて大暴落。
退職金の半分近くを失ってしまいました。
【教訓】
退職金の運用は、老後の生活資金を減らさないことが最優先です。
リスクの高い投資商品に全額を投じるのは非常に危険といえます。
まずは、元本が保証された預貯金や国債など安全性の高い資産で一定額を確保し、余裕資金の範囲内でリスク資産を検討するなど、リスクとリターンのバランスを意識することが重要なのです。
Q&A|退職金に関するよくある疑問
ここでは、退職金に関して多くの方が疑問に思うことについて、Q&A形式で解説します。
Q1:退職金は「一時金」と「年金」どちらが得ですか?
A1: どちらが得かは、個人の状況によって異なります。
一般的には、退職金の額が大きく、勤続年数が長いほど、税制優遇が大きい一時金で受け取る方が手取り額が多くなる傾向にあります。
しかし、年金形式で受け取った場合、受け取り開始から最終受け取りまでの間に運用益が発生し、総額が一時金を上回ることもあります。
また、浪費癖がある方や、計画的に生活したい方は年金形式の方が向いているかもしれません。
まずは、勤務先の退職金制度を確認し、税金シミュレーションを行うことで、あなたのケースでどちらが有利かを確認しましょう。
Q2:退職金を運用するとき、NISAやiDeCoは使える?
A2: はい、NISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)は退職金の運用に活用できます。
NISA(新NISA)は、年間最大360万円の非課税投資枠があり、生涯にわたって非課税で運用できる非常に優れた制度です。
退職金というまとまった資金を、非課税で効率的に運用するのに最適でしょう。
一方、iDeCoは65歳未満の国民年金被保険者などが利用でき、掛け金が全額所得控除になるという大きなメリットがあります。
ただし、60歳まで引き出せない、一度にまとまった金額を拠出できないといった制限もあるため、あなたの状況に合わせて検討が必要です。
Q3:退職金の相談はどこにすればいい?(銀行・FP・証券会社)
A3: 退職金の相談先は、それぞれ得意分野が異なります。
✅銀行・証券会社
- ◎メリット:金融商品の提案や手続きに詳しく、豊富な選択肢の中から具体的な運用方法を相談できます。
- ×デメリット:自社の商品を勧めてくる可能性があるため、必ずしも中立的なアドバイスとは限りません。
✅ファイナンシャル・プランナー(FP)
- ◎メリット:個人のライフプランや家計状況を総合的に分析し、中立的な立場から客観的なアドバイスをしてくれます。
- ×デメリット:相談料がかかる場合があります。また、FPによって得意分野が異なるため、退職金や資産運用に詳しいFPを選ぶ必要があります。
まずは銀行の窓口やセミナーなどを利用して大まかな情報を集め、より個別の状況に合わせたアドバイスが必要であれば、信頼できるFPに相談してみるのがおすすめです。
まとめ|退職金を安心して活かすためにできること

退職金は「一括」「分割」「運用」それぞれに特徴があり、どれか一つが絶対に正解というものではありません。
大切なのは、あなたや家族のライフプランに合わせて組み合わせを考えることです。
この記事のポイントを整理すると、以下のようになります。
まずは退職金制度を把握する
あなたの勤務先の退職金制度が、一時金と年金どちらに対応しているか、また税金のシミュレーションができるかを確認しましょう。
老後の生活設計を具体的に立てる
毎月どれくらいの生活費が必要か、将来の大きな支出(住宅リフォームや介護費用など)はどのくらいかかるかを具体的に計算しましょう。
税金の仕組みを理解する
退職所得控除や公的年金等控除の仕組みを理解し、手取り額がどう変わるのかを把握しておくことが重要です。
運用は無理のない範囲で
老後資金は「減らさない」ことが基本です。
まずは安全な資産で確保し、余裕資金の範囲内で無理のない運用を検討しましょう。
専門家を頼る
迷うことがあれば、銀行やFPなど専門家の力を借りることも有効です。
複数の専門家に相談し、中立的な意見を聞くことも大切でしょう。
退職金を「ただ受け取るお金」ではなく「未来の生活を支える資産」として考え、シミュレーションや準備を行いながら最大限に活かしていきましょう。
もし退職金の受け取り方について迷っている場合は、まずはあなた自身の勤続年数を確認し、税金のシミュレーションから始めてみてはいかがでしょうか?
【免責文】ご確認ください 本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度や税制、商品の内容は変更される場合があります。最終判断は、必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて税理士・ファイナンシャルプランナー・医師などの専門家へご相談ください。当サイトは、本記事をもとにした行動の結果について責任を負いかねます。
